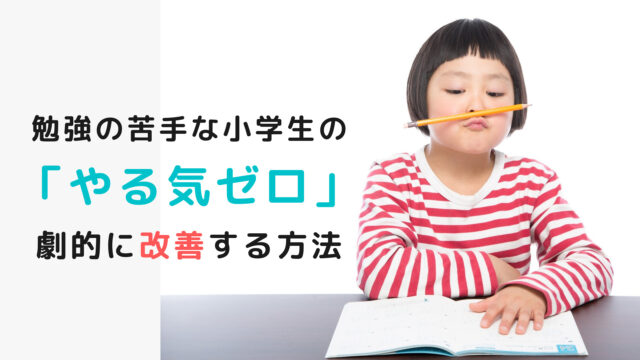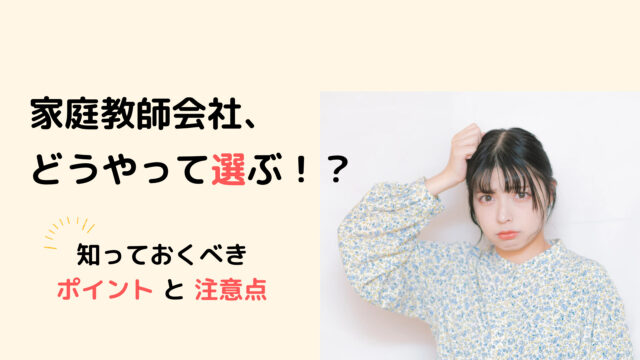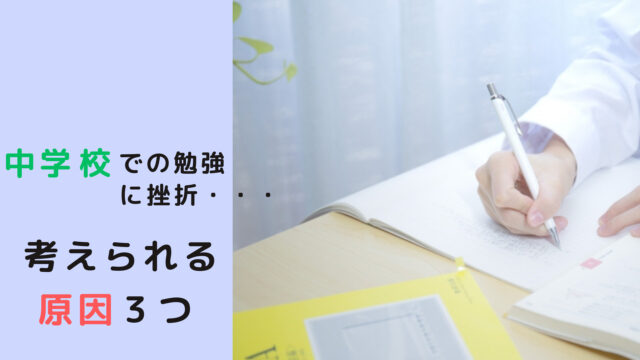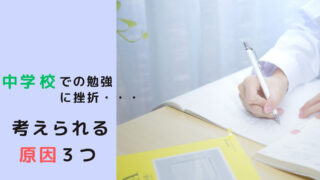「着替えを嫌がる」
「お風呂になかなか入りたがらない」
など、お子さんの困った行動に頭を抱えている親御さんに、これまでたくさん出会ってきました。
今回は、子どもの困った行動(というより不思議な行動?)に私がどのように対処しているか、ご紹介してみたいと思います。
「机の下にもぐる」不思議な生徒さんとの出会い
発達障害グレーゾーンのお子さんを担当し始めた駆け出しの頃、不思議な生徒さんに出会いました。
彼女は、いざ授業が始まると、机の下にもぐってしまうのです。
「授業を受けたくないのかな?」と最初は思いましたが、そうでもない様子。まだ言葉も拙い彼女でしたが、わたしは対話を重ねることにしました。
すると、どうやら「机のライトが眩しすぎる」ことが原因だということがわかってきたのです。
子どもの行動の「背景」を知ることの大切さ
お子さんが、困った行動を何度も何度も繰り返したとしたら。
余裕がないときであれば、叱りたくなってしまうかもしれません。
もちろん、困った行動によってお子さんの身に危険が迫るような緊急性がある場合は、叱ってでも止める必要があります。しかし基本的には多くの場合、「叱るよりも有効な解決方法がある」と私は考えます。
それは、困った行動の「背景に何が隠れているか」を知ることから始まります。
ステップ① 困った行動が起きる状況を「観察」する
困った行動が起きる状況を、よく観察してみましょう。
- 困った行動が起きる「場所」は決まっているか?YESなら、そこには何があるか?
- 困った行動が起きる「曜日」や「時間帯」は決まっているか?YESなら、その日その時間に、何があるか?
- 困った行動が起きる「前」に対処することは可能か?
観察によって、困った行動の背景にあるものが見えやすくなります。
ステップ② 子ども本人と「対話」をする
状況の「観察」を通して、困った行動の背景にあるものの仮説が立てられたら(あるいは全く解らない場合もありますが)、次はお子さんとの対話です。
1.背景の確認
「もしかして、机のライトが眩しい?それとも、椅子に座っているのが落ち着かないのかな?」
↓
2.解決方法の相談
「どうしたらいいと思う?」
「机のライトを、変えてみるのはどうかな?」
お子さんの発達状況や性格に応じて、自分で解決方法を考えてもらったり、2つの提案をして2択で選んでもらったり、私は対話方法を少しずつ変えるようにしています。
最後に
冒頭に挙げた「机の下にもぐる」生徒さんは、机のライトの明るさを調整することによって、机で勉強をするようになりました。
お子さんと対話を重ねるというのは、地道で大変な作業だと思います。叱ってやめさせた方が、短期的な視点で見ると早いかもしれない。
しかし私は、この対話のプロセスを大切にすべきだと思っています。
親御さんだけで解決が難しい場合は、専門の療育機関に相談してみるのも良いかもしれません。親子のコミュニケーションがより豊かなものになるよう、祈っています!