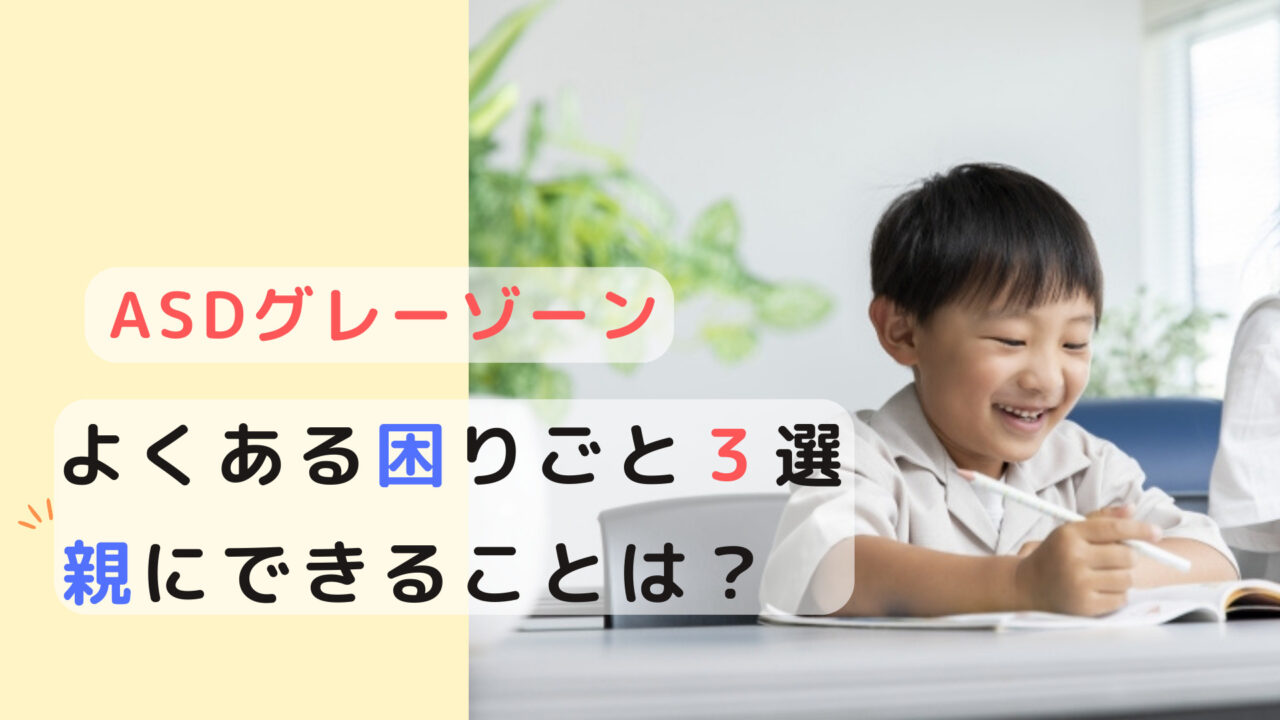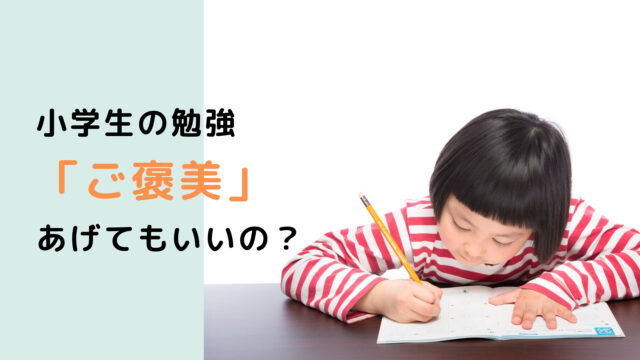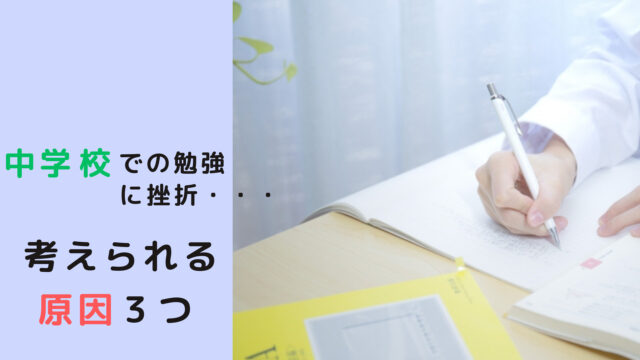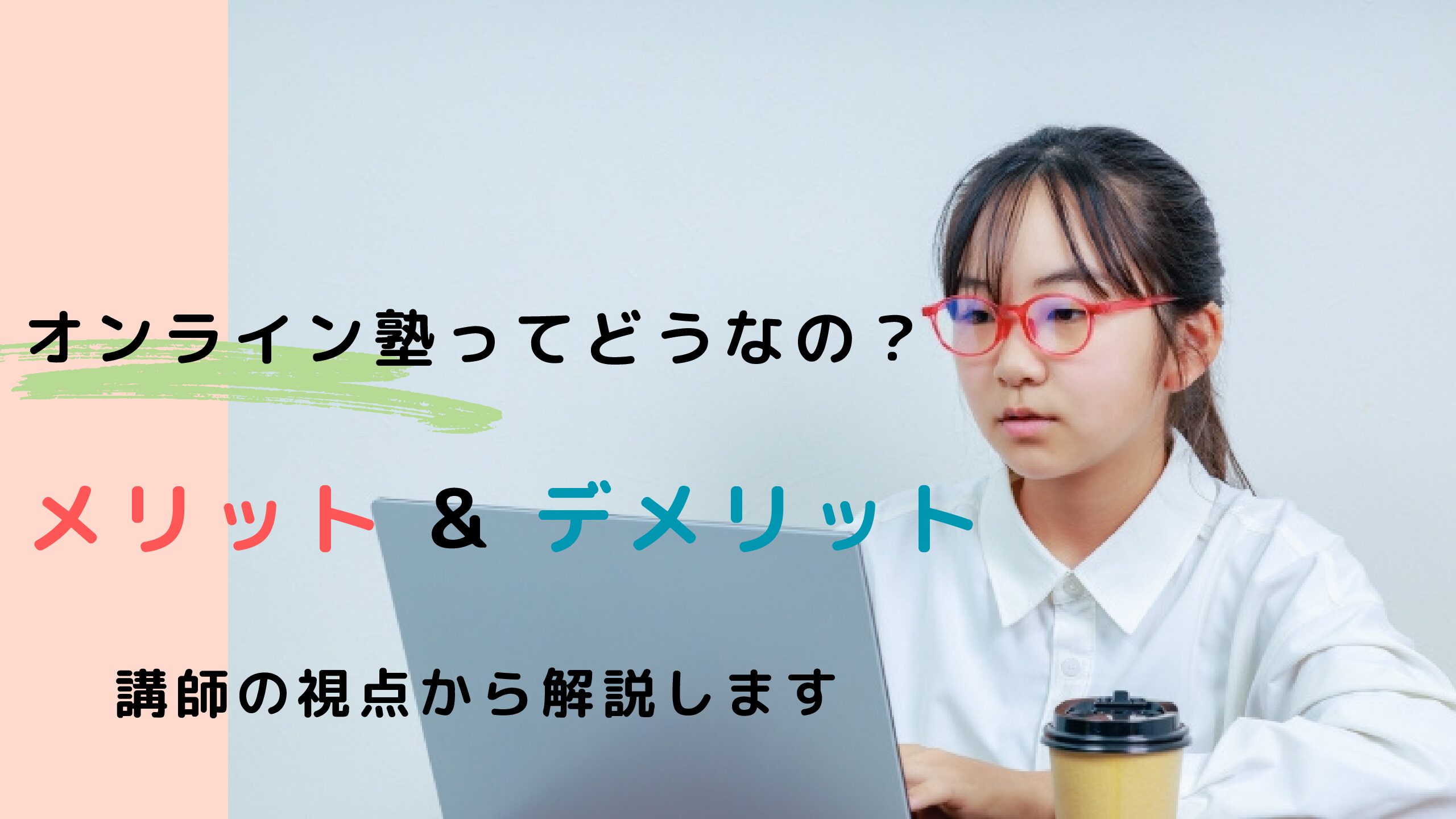ASD(自閉スペクトラム症)グレーゾーンとは、「ASDの特性を持っている傾向があるが、医療機関で診断されるほどではない」ことを指す言葉です。医学的な名称ではないものの、世間一般に使われている表現です。
ASDグレーゾーンの子どもたちは、
- 対人関係を築くことが苦手
- 興味や行動が限定している
- 特定の強いこだわりを持つ傾向にある
といったASDの特性を持ちながらも、通常学級の中では苦手なことをしなければならない場面が多くなりがちです。本人は頑張っているのに、「◯◯ができないのは本人の努力不足だ」と周りから思われてしまったり、「自分は頑張ってもできない人間なんだ」と本人が劣等感を持ってしまったりといったことが起こります。これは、グレーゾーン特有の悩みといえるでしょう。
今回は、通常学級での学習でASDグレーゾーンの子どもたちが抱えやすい困りごとと、それに対して親ができるサポートについて、お話していきます。
Contents
ASD(自閉スペクトラム症)の学習面での困りごとと対処法
困りごと① 読みたい本の種類や内容が限定される
ASDグレーゾーンのお子さんは、読みたい本の種類や内容が限定されていて、なかなか他の本を読みたがらないことがあります。たとえば私の生徒の例では、学校から配られた「防災パンフレット」を繰り返し音読しているお子さんがいらっしゃいました。
興味を広げる工夫をする
少しずつ、興味を広げていきましょう。少しずつといっても、具体的なポイントがあります。
「興味を持っていること」と「現時点では興味を持っていないこと」を、リンクさせていくのです。
たとえば先ほど挙げた防災パンフレットの中には、「雪がとけ始めたときが危ない」という内容のページがありました。ここから、「水の状態変化」など科学本につなげても良いでしょうし、「雪って日本のどの辺りで降りやすいのかな」と地理の内容に持っていくこともできます。雪が出てくる物語にも興味を持つかもしれません。
お子さんと対話しながら、次に興味の出てきそうなジャンルを一緒に見つけてあげてくださいね。
困りごと② 知らない学習内容に出会うことを嫌がる
ASDグレーゾーンのお子さんは、知らない学習内容に出会うと嫌がることがあります。
事前に「予告」と「見える化」
前々から、「今日の◯曜日は、新しいことを勉強するんだよ」を予告し、心の準備をさせてあげましょう。事前に伝えてあげることで、びっくりしにくくなります。
新しいことを学ぶ当日には、これから取り組むことを「見える化」してあげるとよいでしょう。見通しが立っていれば、お子さんは安心感を持って学習に取り組めます。
声かけの仕方を統一し、曖昧な言い方は避ける
たとえば、「『3分の2』は『3つに分けたうちの2つ分』です」というように、決まった言い方で伝えます。
困りごと③ 100点じゃないと気が済まない
ASD傾向があり勉強に苦手意識がついているお子さんに多くみられます。
こだわりが強いうちは、100点を取らせてあげてOK
お子さんが解いたプリントが間違いだらけだったとしたら、「見直しの練習」と言って一緒に見直しをしてあげてください。間違いだらけのプリントをそのまま丸つけしてしまった場合、丸の数が少なすぎて「もう嫌だ!」となりがちですので、一緒に間違い直しをしてから丸つけをさせてあげるのです。
勉強への苦手意識が薄らいできたら、100点へのこだわりは次第になくなってくるケースもあります。
親御さんのサポートだけでは難しい場合の選択肢
グレーゾーンの子どもたちが抱えやすい困りごととその対処法、いかがでしたか?グレーゾーンのお子さんを持つ親御さんの中には、「どう声かけをしたら良いのか分からない」「自分の子どもへの対応が正解なのかどうか分からない」などといったお悩みを抱えている方がたくさんいます。
親御さんのサポートだけでは難しいと感じる場合には、外部に相談してみるのも一つの手です。相談を行なっている機関について紹介した記事も、参考にしてみてくださいね。