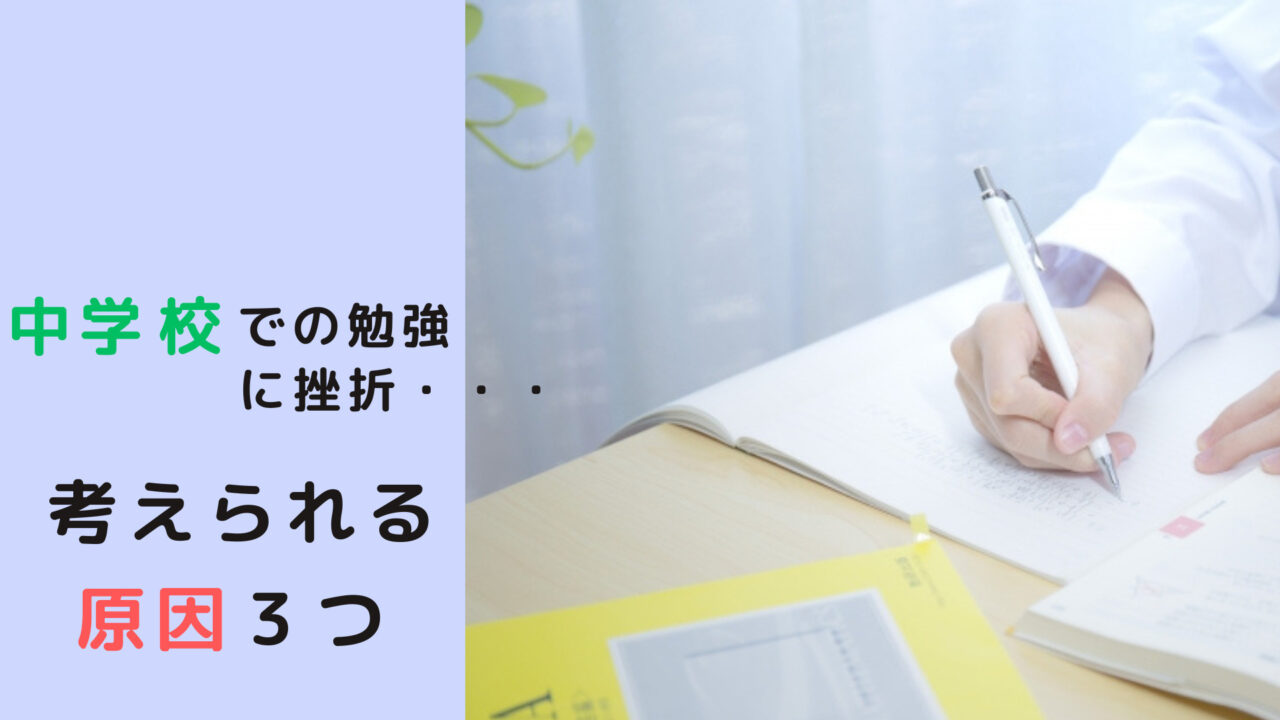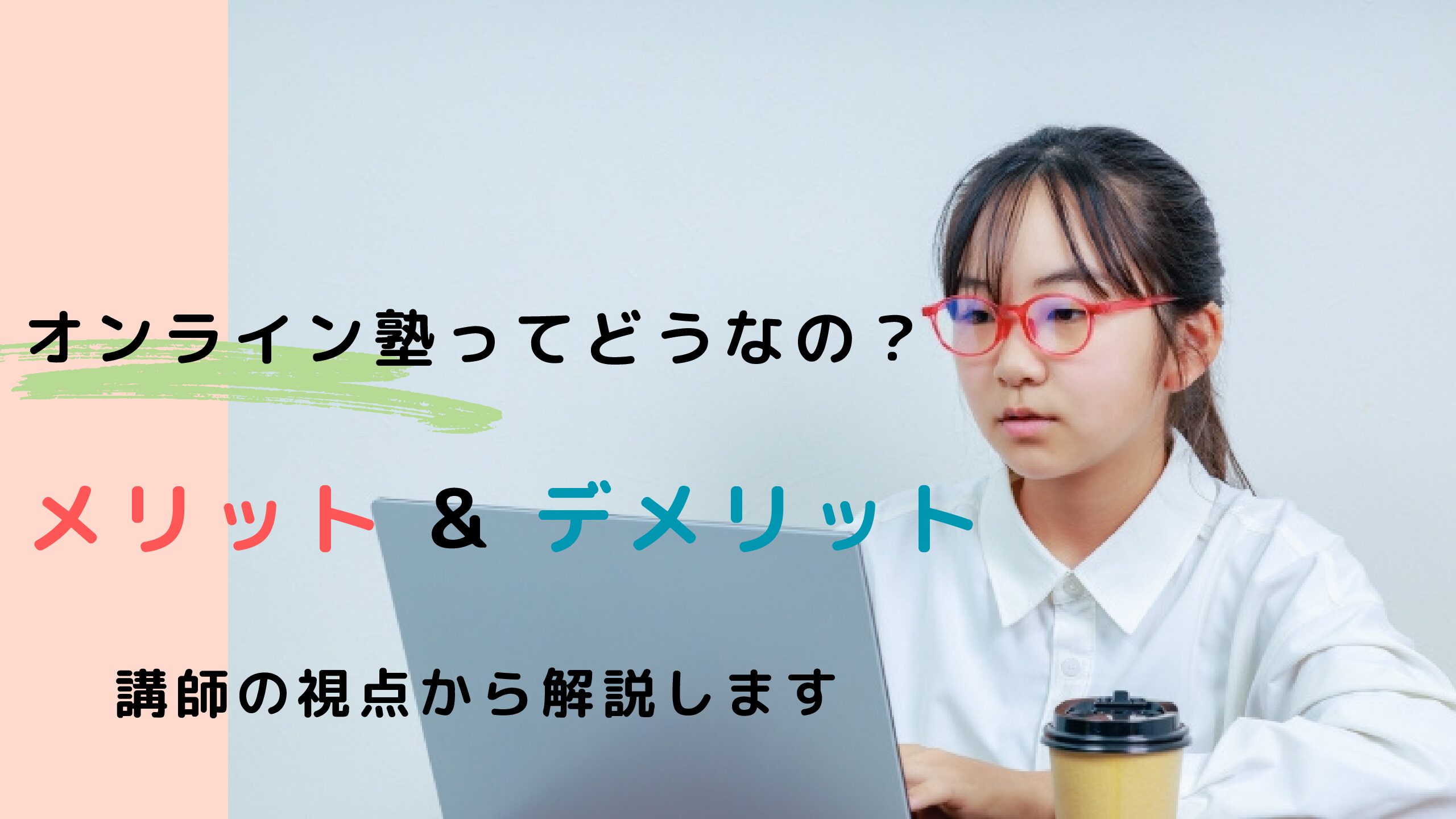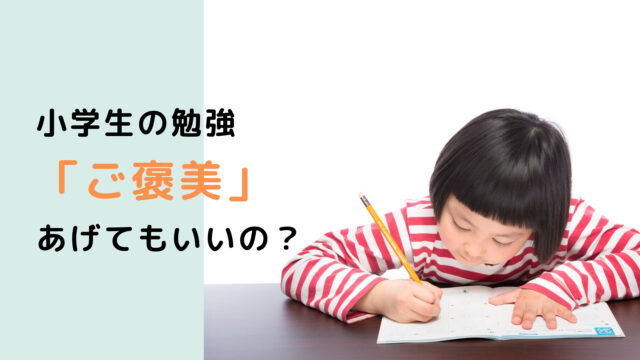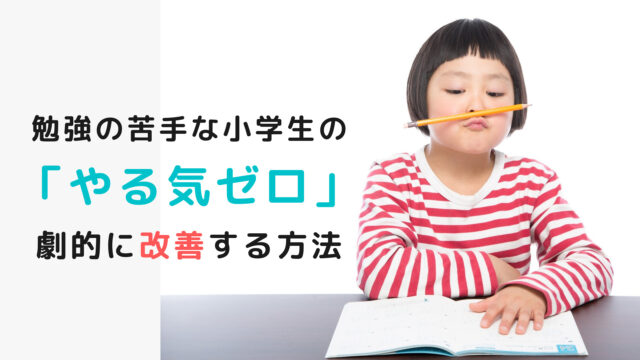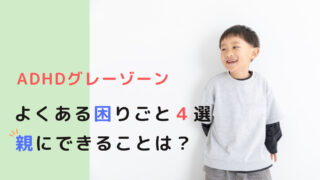「小学校の成績はまずまずだったのに、中学校に上がった途端に成績が下がった」
「勉強についていけなくなった」
このように、中学校に入った途端に挫折してしまうケースは、実際よくあります。
今回は、考えられる原因を3つ紹介します。
Contents
中学校の勉強で挫折しやすい3つの原因
原因① 小学校と中学校では、テストの頻度と範囲の広さが違うから
小学校のテストは「カラーテスト」と呼ばれ、単元ごとのまとめの内容になっています。一年間に習う単元数は、学年や使っている教科書会社にもよりますが、15〜20単元ほど。つまり、一年間に15〜20回ほどのカラーテストがあります。
一方、中学校のテストは「定期テスト」と呼ばれ、一年間に数回しかありません。
一年間に数回しかないということは、当然一回分の範囲が広いということであり、範囲が広いテストの勉強をすることに慣れていないうちは、とても大変なことなのです。
さらに、学校により頻度は異なりますが、中学校ではこの定期テストに加えて、授業内での小テストが行われることがほとんどです。
原因② 小学校と中学校では、提出物の多さや指示の分かりやすさが違うから
小学校のうちは、担任の先生が宿題の指示をしてくれるため、少なくとも「何が宿題で出ているか」は分かっていたことでしょう。
しかし中学校に上がると、宿題は「教科ごとでの指示」になり、情報量が格段に多くなります。
実際私も、小学校のうちは提出物を出せていたのに、中学校に上がった途端にパンクしてしまったというお子さんを何人も見てきました。
中学校では、学校の宿題のサポートだけでもかなり大変です。
原因③ 思春期に突入するから
中学生は、思春期の真っ只中。親や教師に対する反抗心や、「これは嫌だ、やりたくない」「勉強のやり方は自分で決めたい」等自分の考えもはっきりしてくる時期です。
もちろん、これは発達上大切なプロセスです。
しかし、新しい教師との間で「信頼関係を築くまでに時間がかかる」ということが、学習においてマイナスに働いてしまう場合があります。
小学生のうちはまだ感情が見えやすいため、信頼関係を築く前の段階でも、コミュニケーションは比較的取りやすいです。一方で中学生の場合では、教師側から生徒の感情を読み取るのが難しくなる場合が多いです。以下のような例です。
教師「明日までにこの宿題やっておいてね」
生徒「分かりました!(本当は絶対やりたくない・・・!)」
教師「(うんうん、素直な子だなあ)」
まとめ
数学や英語といった積み上げ型の科目は、一度つまづくと後が大変です。
苦手意識が定着してしまう前にお子さんと話し合い、一年生の一学期だけはプリントの整理を一緒にやる、塾や家庭教師を検討する等の対処を考えることが大切です。