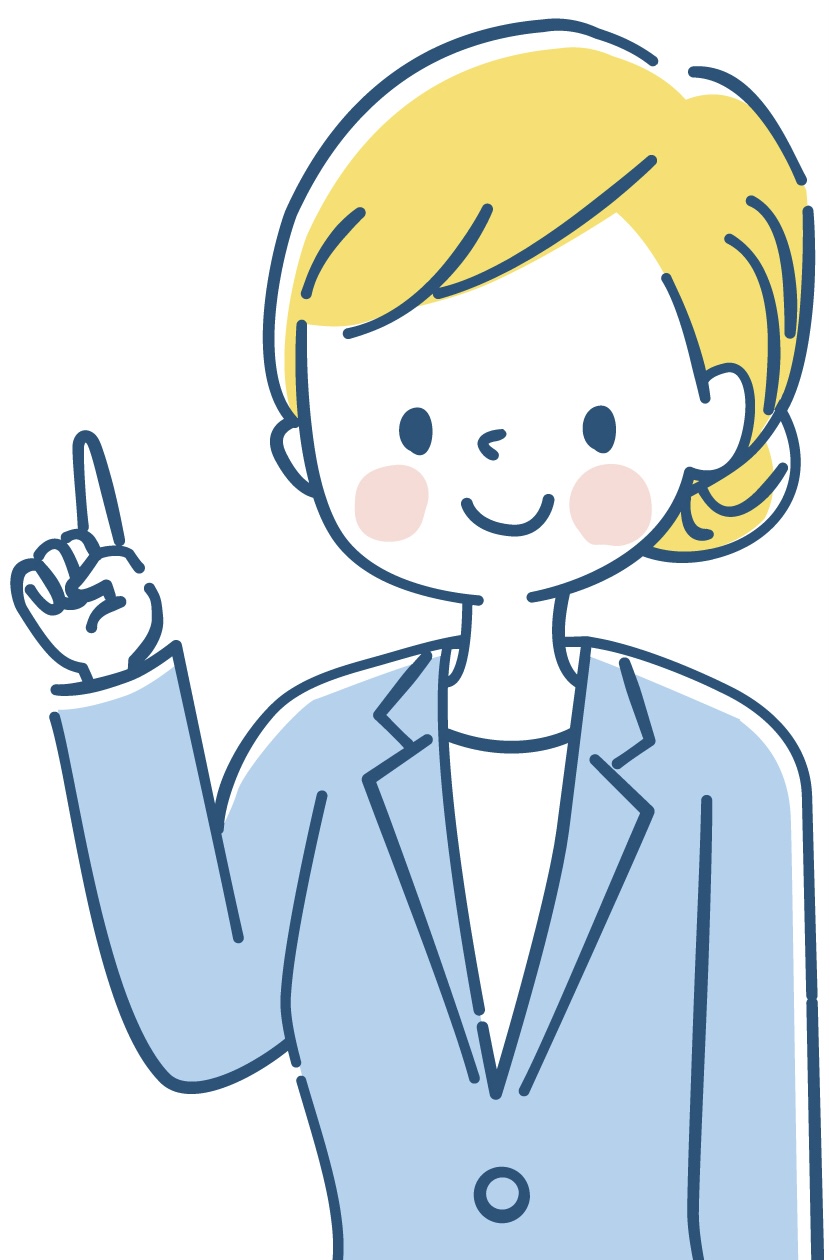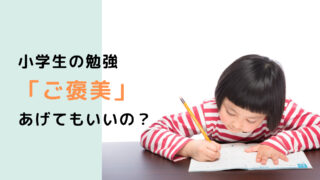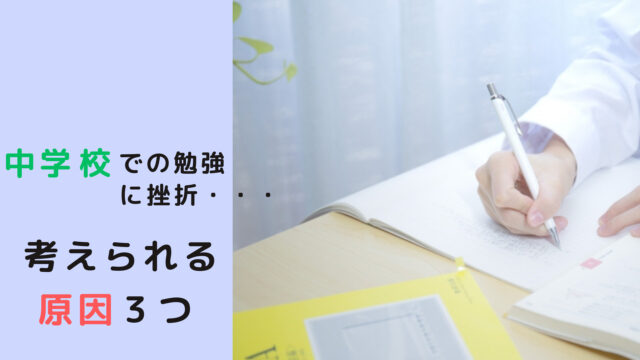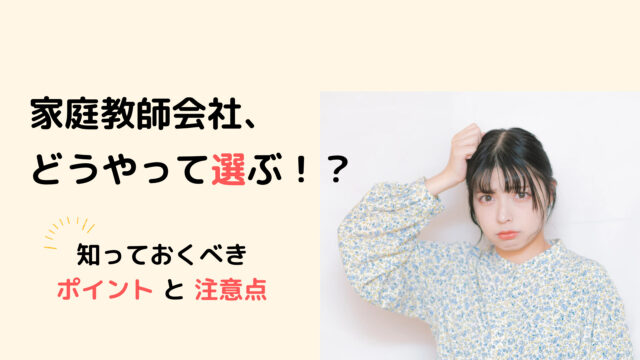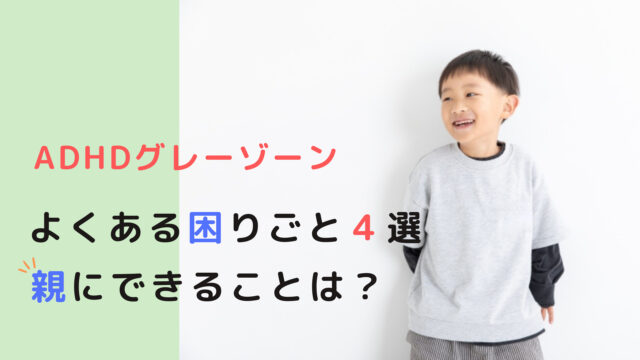もっとも大切なのはズバリ、「泣き出す前の対応」なのです!
〜〜〜
私は、プロ家庭教師として発達障害グレーゾーンのお子さんを中心に学習指導を行ってきました。10年以上前に、LD(学習障害)を持つ生徒を担当した経験から教育に携わることを決意し、さまざまな特性を持つ生徒さんに合わせたカリキュラムや声かけの方法を模索し続けてきました。今では、テストで30点しか取れなかったお子さんでも、安定して80〜90点を取れるように指導が出来るまでになりました。
〜〜〜
本記事では、お子さんが「勉強で泣き出してしまう」ときの、とっておきの対処法を紹介します。
Contents
勉強で泣き出す「前」に対策を!
勉強で泣いてしまう子どもへの対応として、一般的によく言われるのは、以下のようなことではないでしょうか?
「まずは落ち着くまで待ちましょう」
「どこがわからないのかを聞き、つまづいている問題よりも簡単な問題からスモールステップで取り組ませて、成功体験を積ませてあげましょう」
「できたらほめる、を繰り返しましょう」
しかし子どもの行動を変えていくためにまず最初にやるべきことは、「泣きだしてしまう前に適切な対処をする」ことなのです。
「こうすれば泣かなくなる!」解決までの具体的なステップ3つ
STEP1 「なぜ勉強で泣いてしまうのか?」原因を分析しましょう
お子さんが泣き出してしまうのは、なぜなのでしょうか?
「勉強が分からない、解けないから」
「間違えてしまったから」
「勉強をやりたくない、めんどくさいから」
とにかく、まずは泣き出してしまう場面を思い返し、原因を探ることがポイントになります。
STEP2 勉強で泣き出す「前」の対処法を考えましょう
STEP1で挙げた原因別に、おすすめの対処方法をお伝えします。
よくある原因①「勉強が分からない、解けないから」
泣き出してしまうほど分からない。そんなとき、子どもは「どうせ出来ない」「難しすぎる」という考えに囚われています。
このような状態のときに、丁寧に「教える」ことは実はNGなのです。
それでは、どうすればよいのでしょうか?
こういった場合、まずは考え方を教えるのではなく、「解き方の手順を見せて真似をさせる」のが有効です。
そんな声が聞こえてきそうです。
しかし、「分からない」と泣き出してしまうほど苦手意識を持っているお子さんに対しては、まずは「分かる」「できる」という経験を持たせてあげることが最優先。
考え方を教えるのは、その後でよいのです。
「一人で出来た」経験は、自信となります。
よくある原因② 「間違えてしまったから」
間違い直しを嫌がるお子さんはとても多いですが、極端な場合、一問でも間違えると泣き出してしまうケースも。
このような場合には、「丸つけ」の前に「見直し」を一緒にやってあげましょう。
一緒に見直しをしながら、「自分で間違いに気づけた!」という成功体験を増やしていくのです。
「見直し」だから、見つかった間違いは赤ペンではなく鉛筆で書き直してOKです。
そして最後に丸つけをしてあげます。
見直しの段階で間違いが直っているので、気持ちよく花丸をつけてあげられるはずです。
よくある原因③「勉強するのがめんどくさいから」
「めんどくさい」を解消するには、学習へのモチベーションをコントロールする必要があります。こちらについては別記事にまとめましたので、そちらをご覧ください。
STEP3 自然と勉強するようになるまで、STEP1→2を繰り返しましょう
望ましい行動を定着させるには、STEP1(泣いてしまう原因探し)→STEP2(効果的な対処)を何度か繰り返す必要があります。
実はこの方法は、他にも生活習慣や問題行動の改善など、さまざまなことに応用できます。詳しくは、別記事にまとめます。
まとめ
いかがでしたか?
普段私が使っている方法を紹介しましたが、「お母様・お父様には甘えてしまってなかなかうまくいかない」ということもあると思います。
そんなときには、塾や家庭教師の先生にお願いするのも一つの手です。
お母様・お父様とは異なる関係性の人間が入ることで、お子さんの行動が変わるきっかけになるかもしれません。