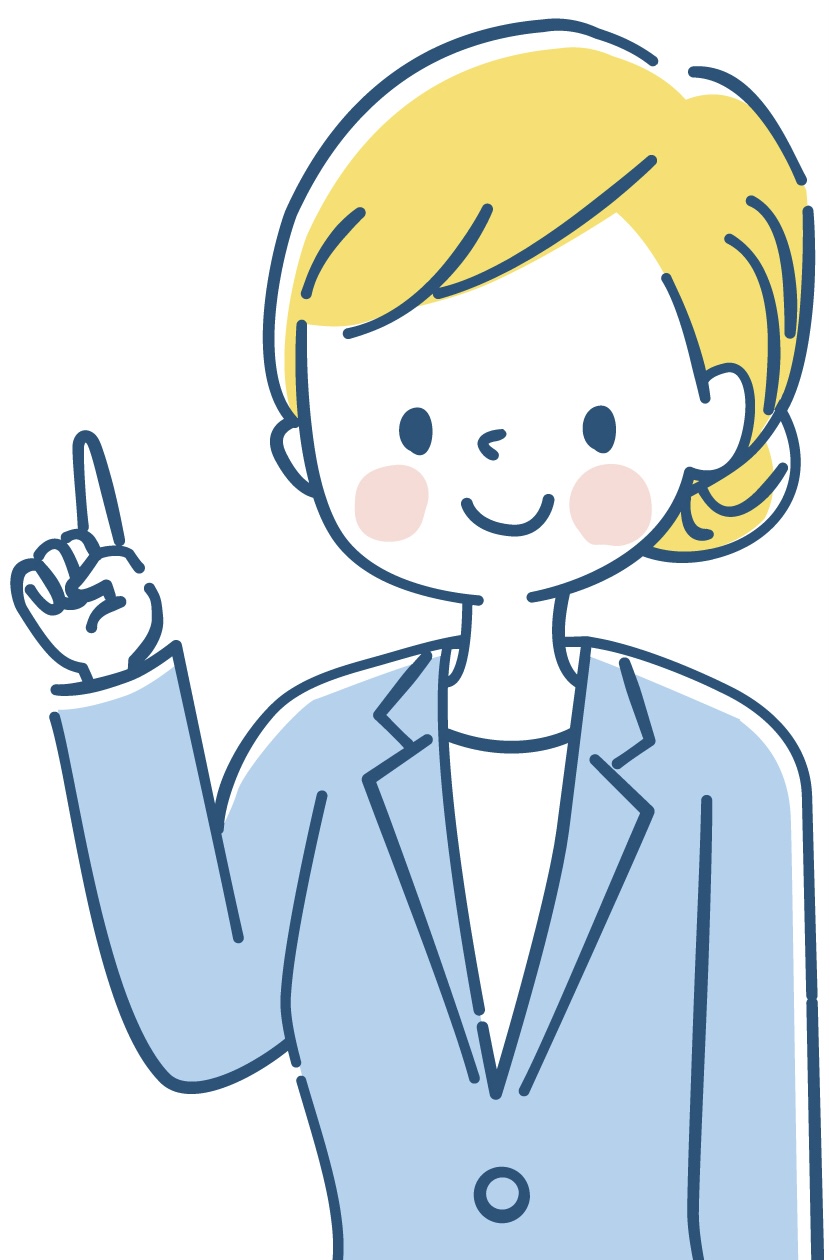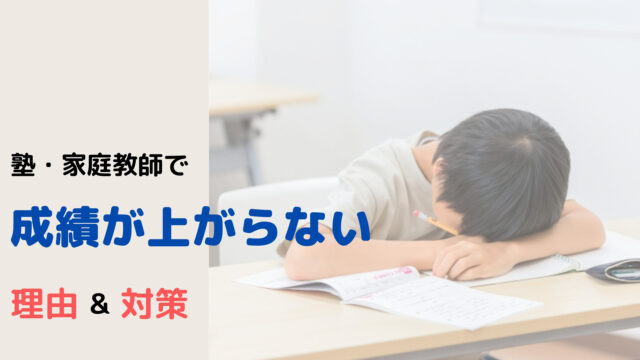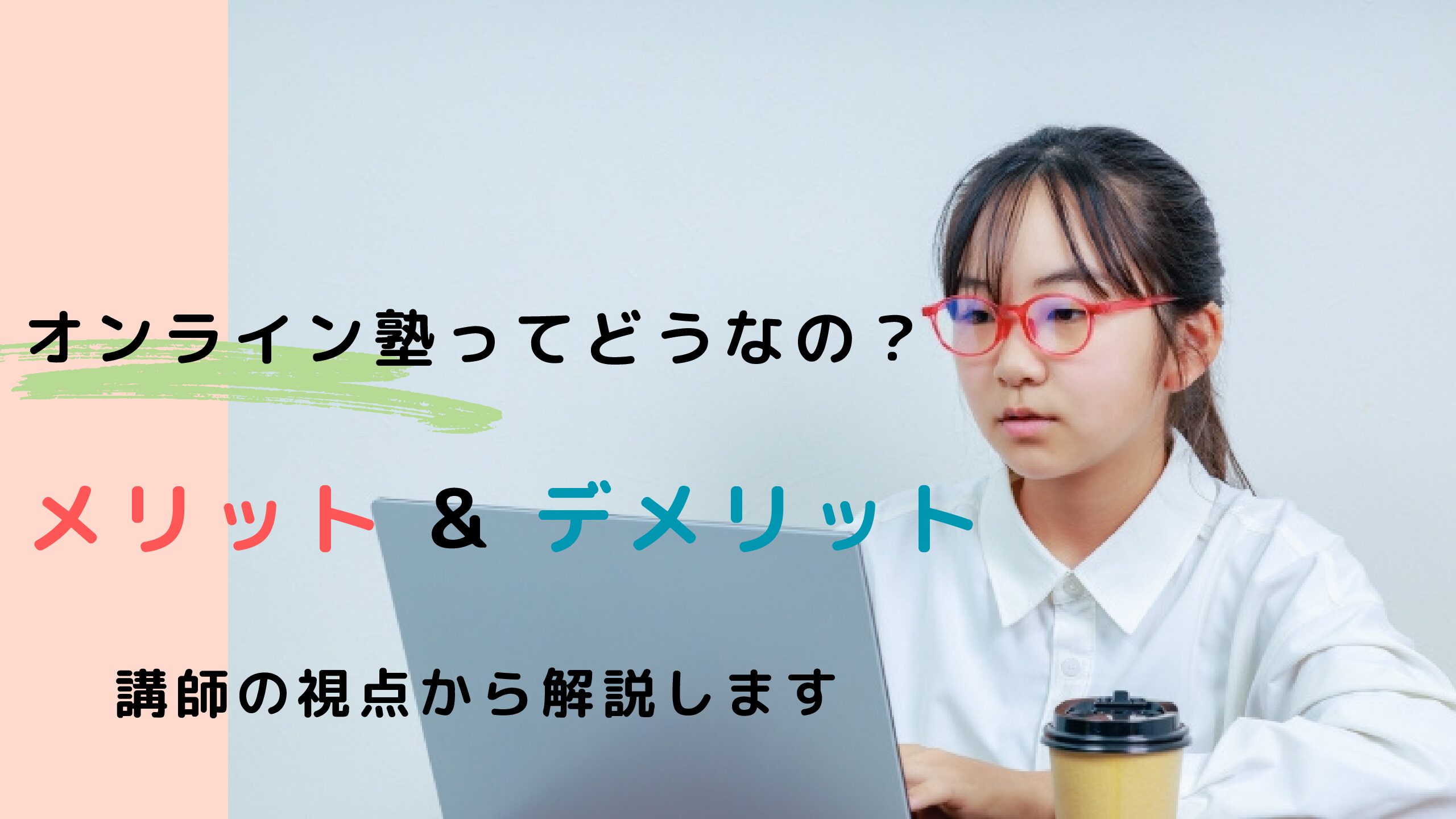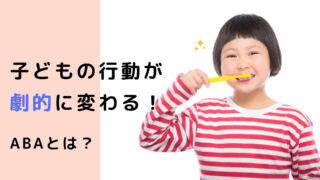・小学生が音読を嫌がるワケとは?
・音読が苦手な小学生、どうすれば取り組んでくれる?
・音読が苦手だと、他の教科にどう影響する?
・音読の次のステップは?
私は、プロ家庭教師として発達障害グレーゾーンのお子さんを中心に学習指導を行ってきました。10年以上前に、LD(学習障害)を持つ生徒を担当した経験から教育に携わることを決意し、さまざまな特性を持つ生徒さんに合わせたカリキュラムや声かけの方法を模索し続けてきました。今では、テストで30点しか取れなかったお子さんでも、安定して80点以上取れる指導ができるまでになりました。
Contents
音読のニガテ原因別・クセ別に、対策をすべて紹介
1. 音読を嫌がる「原因別」対策4つ
なぜ音読が嫌なのか?お子さん本人に聞ける場合は、ぜひ聞いてみましょう。
お子さんとの対話から、思わぬ原因が見つかることもあります。
音読を嫌がるワケ① たくさん間違えたりつっかえたりする
こういった声をよく聞きますが、私がいつもお伝えするのは、
「間違えたりつっかえたりした後に助けるのでは、間に合っていない」ということです。
なぜなら、すでに音読に対してニガテ意識を持っている子どもに対して、
「間違えたりつっかえたりした経験をこれ以上積ませては逆効果」だからです。
そこで、以下の方法を試してみてください。
・文章を目で追わせながら、先にお手本として大人が読んであげる。そのあとに続いて、子どもに読ませる。
・同じ文章を繰り返し読ませ、ミスが減っていく達成感を持ってもらう
慣れないうちは、無理なく一文二文程度から始めてもOKです。
慣れてきたら、三文以上まとめてお手本を示してから読ませる、ということを繰り返します。
音読を嫌がるワケ② 文章が長すぎる
こういった声もよく聞きます。このようなケースでは、以下の対策を試してみてください。
・全体の文章量を調整してあげる。文章量が決まっている宿題等の場合は、何回かに分けて取り組む。
宿題の音読の範囲が決まっていても、必ずその通りにしなければならないということはありません。読む量を調整しても良いか、学校の先生に相談してみることをおすすめします。
音読を嫌がるワケ③ 興味が持てない
説明文だけにニガテ意識のあるお子さんも、たしかにいらっしゃいますね。
このような場合は、以下のステップを踏ませてください。
・興味の持てる分野を探し、レベルに合った説明文を読ませる(例:生き物の生態)
・上の分野と、関連性はあるが少しだけ違う内容のものを読ませる(例:人間の進化)
・少しずつ内容をずらしていきながら、読める分野を増やしていく(生き物の生態→人間の進化→人間の進化と環境問題→・・・)
ぜひ、選書のプロである学校の司書さんに相談してみてください。お子さんにぴったりの本を紹介してくれるはずです。
また、まだまだ精度が高いとは言えませんが、Chat GPTに「小学生向けのお話を書いて」と相談してみるという方法もあります。この方法の良いところは、字数を指定できるという点です。
音読を嫌がるワケ④ 文章がゆらいで見える・滲んで見える
気づかれにくいのが、この「他人と違った見え方をしている」というパターン。
このような場合は、専門のクリニックに相談してみるのも一つの手です。メガネの調整で、一気に改善したという例もあります。
2. 音読の「クセ別」対策6つ
音読のクセ①「行を丸々飛ばす or 同じ行を読んでしまう」
以下の対策がオススメです。
・読んでいる行の次の行を、ものさし等で隠しながら読んでみる
・線を引きながら読んでみる
こうして練習しているうちに、だんだんと補助なしでもできるようになる子が多いです。
音読のクセ②「文の一部を勝手に変えて読んでしまう」
「文の最後まで丁寧に読もう」と言っても、子どもたちには伝わりづらいもの。
「丁寧に」という言葉は、子どもにとってはあまりに抽象的で分かりにくいからです。
このようなときは、より具体的な形で、「身体の動きを指示してあげる」のが効果的です。
以下のような対策を試してみてください。
・読むと同時に線を引いていく
・スラッシュで区切りながら読む
このように「身体の動き」をつけてあげることで、読むスピードがコントロールしやすくなります。
音読のクセ③「漢字や難しい語彙が読めない」
これに関しては、残念ながら近道はありません。毎日の積み重ねが必須です。
(オススメの問題集については、また別記事にて解説します。)
・毎日少しずつ問題集に取り組む
ただし、「漢字がニガテだから漢字ドリルを」という考え方には注意が必要です。
漢字がニガテなお子さんがいきなり漢字ドリルに取り組むのは、心理的ハードルが高いため、なかなかうまくいかない場合もあります。
上手に語彙を増やせるような教材選びをしたいものですね。
教材選びのポイントは、「無理なく漢字や語彙を学べるか」ということ。
例えば、公文の「いっきに極める熟語」シリーズは、分からない漢字が出てきた場合にも、同じページ内を探せばすぐ答えが見つかるようにデザインされており、オススメです。
音読のクセ④「文の区切りがおかしい」
例えば、「もっとも よいもの」を、「もっと もよいもの」などと読んでしまうケースです。
文の区切りがおかしいお子さんは、③で述べた「語彙が足りていない」ケースの他に、「ただ単に文章を読む練習量が足りていない」ケースに分かれます。
「ただ単に文章を読む練習量が足りていない」ケースでは、以下のような方法を試してみてください。
・一緒に読みながら、区切り方が難しい箇所にスラッシュを入れてあげる
音読のクセ⑤「読むことと理解することが同時にできない」
脳科学によると、子どもの脳はまだまだ未熟で、「記憶しないと理解が進まない仕組み」になっているそうです(大人は「理解しながら記憶していく」ことが可能)。
言い換えると、声を出すことだけに一生懸命になってしまっているのです。
そこで、このような練習を試してみてください。
・同じ文や文章を繰り返し音読し、暗唱できるくらいまで何度も練習する
一度頭に入った状態での音読を繰り返すことで、考え理解する能力を育てることができます。
音読のクセ⑥「一文字ずつしか読めない」
例えば、「くるま」という単語のまとまりではなく、「く」、「る」、「ま」のような読み方です。
・助詞(は、が、と、を、等)に丸(またはマーカー)をつけながら読む
この方法を使うと、名詞と助詞の区切りが分かりやすくなるため、理解しやすくなります。
また、「助詞だけを強く読む」練習を、遊びとして取り入れるのもオススメです。(ただし、こだわりの強いお子さんの場合はクセになってしまう可能性がありますので、やり過ぎに注意してください)
音読が大切である2つの理由
1. 音読こそが、「すべての基礎になる」から
学校の宿題では必ずと言ってよいほど出される「音読」の宿題。
音読が苦手なお子さんをお持ちの親御様からしたら、「これが一番大変なのよ…」とお思いになることも多いのではないでしょうか。
この音読、苦手になってしまうと、必ずすべての教科に悪影響が出てしまうのです。
試しに、社会や理科のテスト用紙をお子さんと一緒に読んでみてください。国語が苦手なお子さんは、そもそも問題文を正確に読めていないはず。
しかし逆に言えば、音読がうまく出来るようになれば、社会・理科も伸びるということなのです。
2. 音読で「自分の声を聴くこと」こそが、「脳に記憶を定着させる」方法だから
脳に記憶として定着させる最強の方法は、「自分の声を聴くこと」です。子どもは、自分の声を聴くことで受けた刺激を、記憶につなげているのです。
そして音読ができないということは、黙読もできないということ。
学校で毎日教科書を読む時間があると考えると、音読が苦手なお子さんは、一日一日相当な遅れを積み重ねてしまうということなのです。
文字を読むという活動が始まる小学一年生から、音読のできる子・できない子の差がどんどん開いていきます。
音読の次のステップは「黙読」
音読をマスターすれば、黙読をするときにも頭の中で強弱や抑揚をつけながら読むことができるようになるので、理解が進みやすくなります。しかし、中には音読から黙読に移行するのが大変なお子さんもいらっしゃいます。
一番多いのは、「音読から黙読にした途端、スピードのコントロールが効かなくなり、雑に読んでしまう」パターン。音読の場合だと、お子さんの声が聞こえるのでどこが読めていないかすぐに分かりますが、黙読となればそうはいきません。
ですので黙読を取り入れる際には、文章の内容について、親子で会話を繰り広げてみましょう。
「このお話って、登場人物は何人いたんだっけ?」
「主人公の◯◯は、なんでここで泣いちゃったのかな?」
などと優しい雰囲気で聞いてあげてください。
さいごに
音読が苦手なお子さん、特に小学校中〜高学年のお子さんは、すでに勉強面でたくさんの失敗体験を繰り返してしまっている場合が少なくありません。そのような場合は、是非一度外部に相談してみることをおすすめします。
横浜市の家庭教師ココペースでは、メインの学習指導の他、音読のための個別プログラムもご用意しています。発達障害グレーゾーンのお子さんを多数指導した経験のある講師代表と、子ども向けの選書のプロである司書がタッグを組んでお子さんをサポートしています。ご相談だけでも承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。